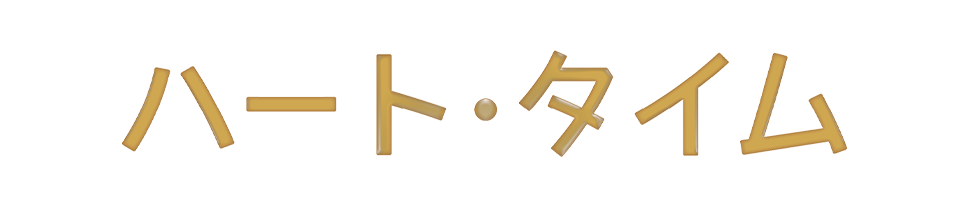春の暖かな陽射しが心地よい季節になりましたね。みなさん、いかがお過ごしですか?
前回は精神障害についてごく一部ですが、お話をさせていただきました。
今回は発達障害について少しお話させていただきます。
テレビやSNSなどで「発達障害」という言葉を見聞きすることが多いと思いますが、「発達障害」とは広汎性発達障害(自閉症スペクトラム)、学習障害、注意欠陥多動性障害など脳の機能発達に関する障害です。「病気」ではなく、「その人の特性」として理解することが大切です。
障害の特性はさまざまありますが、代表的なものとしては以下のものが挙げられます。
・広汎性発達障害
- 自閉症:言葉の発達の遅れ、コミュニケーションがうまくとれない、パターン化した行動やこだわりがあり、急な予定変更が苦手など。
- アスペルガー症候群:基本的に、言葉の発達の遅れはないが、人とうまくコミュニケーションが取れず、対人関係を築くことが苦手。パターン化した行動や興味・関心のかたよりがあるなど。
※それぞれの特性をまとめて現在は「自閉症スペクトラム障害」とよばれることがあります。
・注意欠陥多動性障害(AD/HD)
集中ができず、動き回ってしまい落ち着きがない。衝動的に行動してしまう。
・学習障害(LD)
読み・書き・計算などの特定の領域で遅れがみられる。
※知的発達の遅れは見られないことが多いです。
参考:「厚生労働省:発達障害って、なんだろう? | 政府広報オンライン」
一般的には保育園や幼稚園、小学校くらいで特性が見え始め、学校の先生などから発達障害の疑いのお話がありますが、特性のあらわれ方や程度、環境(周りの理解やサポートの有無)などにより子どものころは発達障害があることに気づかれず、大人になって社会に出たときに、仕事でのつまずき(曖昧な指示をされると理解できず、仕事が進まない。会社の人とうまくコミュニケーションが取れないなど)が生じ、その困りごとのストレスから「眠れない」「気分が落ち込む」「体がダルく、起き上がれない。」など心身に不調を感じ、医療機関を受診した結果、発達障害の特性があることがわかる場合があります。
「できないこと」に目が向けられがちですが、集中力が高かったり、特定の分野における専門知識が豊富、同じ作業を毎日続けられるなど、強みや個性を持っている方も多くいらっしゃいます。
「働きたいけど、なんだかいつも周りの人とうまくいかないな…。」「仕事をしたいのに、長続きしないな…」など働く気持ちがあるけど、どうしたらよいかわからない方でも一度、ハート・タイムへご相談ください。「自分らしく働く」ためにどんなことが得意で、どんな働き方がよいのか一緒にゆっくり考えていきませんか。